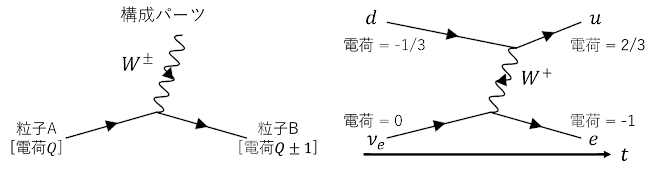5-1. 自由場の量子論 – スカラー粒子 –

これまで素粒子にはフェルミオンやボソン、粒子や反粒子、右巻き左巻きなど様々な分類があることを紹介した。本記事に出てくる最後の分類は、ローレンツ変換に対する粒子の場の変換性である。時空がローレンツ変換するとき、対応する場が 変換しない $\rightarrow$ スカラー粒子 時空と一緒に(4元ベクトルとして)変換する $\rightarrow$ ベクトル粒子 スピノルとして変換する $\rightarrow$ スピノル または ディラック粒子 と分類され、具体的には以下のように整理できる。 本章では、まずスカラー粒子について必要な知識をまとめる。ベクトル粒子、スピノルは自由度が異なるだけで、ここで議論した内容をほぼそのまま使うことができる。 ●単位系 以降、素粒子物理学の慣習に倣って光速$c$とプランク定数$\hbar$を無次元量$1$とする単位系を使用する。これを 自然単位系 という。速さの単位が無次元となるので、次元的には距離 = 時間、エネルギー = 質量となる不思議な単位系であるが、式の見た目はすっきりするし、慣れると次元が正しいか簡単に確かめられるようになる。 この単位系の下では、シュレディンガー方程式やアインシュタインの関係式は以下のようになる。 \[i \frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{1}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2\psi\] \[E^2 = m^2 + p^2\] ●複素スカラー場 自由粒子のシュレディンガー方程式は$E = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}$で$E \rightarrow i\frac{\partial}{\partial t} \ , \ \boldsymbol{p} \rightarrow -i\boldsymbol{\nabla}$の置き換えをすれば得られた。しかし、これは相対論的な形式ではない。近似的には成り立つがこの宇宙の本当の法則を表していない。相対論的な方程式は、アインシュタインの関係式に同様の置き換えをすれば得られる。これを クラインゴルドン方程式 という。 \[(\partial_\mu\partial^\mu + m^2)\phi(x) = 0\] \[\text{但し、}\partial...