5-1. 自由場の量子論 – スカラー粒子 –
これまで素粒子にはフェルミオンやボソン、粒子や反粒子、右巻き左巻きなど様々な分類があることを紹介した。本記事に出てくる最後の分類は、ローレンツ変換に対する粒子の場の変換性である。時空がローレンツ変換するとき、対応する場が
と分類され、具体的には以下のように整理できる。
本章では、まずスカラー粒子について必要な知識をまとめる。ベクトル粒子、スピノルは自由度が異なるだけで、ここで議論した内容をほぼそのまま使うことができる。
●単位系
以降、素粒子物理学の慣習に倣って光速$c$とプランク定数$\hbar$を無次元量$1$とする単位系を使用する。これを自然単位系という。速さの単位が無次元となるので、次元的には距離 = 時間、エネルギー = 質量となる不思議な単位系であるが、式の見た目はすっきりするし、慣れると次元が正しいか簡単に確かめられるようになる。
この単位系の下では、シュレディンガー方程式やアインシュタインの関係式は以下のようになる。
\[i \frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{1}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2\psi\]
\[E^2 = m^2 + p^2\]
●複素スカラー場
自由粒子のシュレディンガー方程式は$E = \frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}$で$E \rightarrow i\frac{\partial}{\partial t} \ , \ \boldsymbol{p} \rightarrow -i\boldsymbol{\nabla}$の置き換えをすれば得られた。しかし、これは相対論的な形式ではない。近似的には成り立つがこの宇宙の本当の法則を表していない。相対論的な方程式は、アインシュタインの関係式に同様の置き換えをすれば得られる。これをクラインゴルドン方程式という。
\[(\partial_\mu\partial^\mu + m^2)\phi(x) = 0\]
\[\text{但し、}\partial_\mu\partial^\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2}-\boldsymbol{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}-\frac{\partial^2}{\partial y^2}-\frac{\partial^2}{\partial z^2}\]
ここで、$\phi(x)=\phi(t, \boldsymbol{x})$は時空の各点$x=(t, \boldsymbol{x})$で値を持つ複素スカラー関数であり、複素スカラー場と呼ばれる。この方程式は、純粋に相対論的な粒子が満たすべき関係式を表している。そのため、後で出てくるベクトル場やディラック場も例外なくこの方程式を満たす必要がある。
(余談)時空の各点で値を持つ関数を『場』というのなら、通常の波動関数も場と言える?
自由粒子の方程式は簡単に解ける。常套手段であるが、$\phi$の空間成分のフーリエ変換を考える。$a(\boldsymbol{k})$および$b^\dagger(\boldsymbol{k})$をフーリエ係数とすることで、
\[\phi(x) = \int\frac{d^3\boldsymbol{k}}{\sqrt{(2\pi)^3 2E_\boldsymbol{k}}} \left(a(\boldsymbol{k})e^{-ik\cdot x} + b^\dagger(\boldsymbol{k})e^{ik\cdot x} \right) \ , \quad E_\boldsymbol{k} \equiv \sqrt{m^2 + \boldsymbol{k}^2} \]
を得る。$k\cdot x$は4元ベクトルの内積$k_\mu x^\mu$であり、$E_\boldsymbol{k}$はアインシュタインの関係式から出てくる運動量$\boldsymbol{k}$を持つ質量$m$の粒子のエネルギーである。$a$と$b$は独立した関数であればいい。数学的にダガーと規格化定数に意味はない(どう設定しようとも方程式を満たす)が、物理的にはダガーは反粒子に対応し、規格化定数は交換関係を簡単にするために決められている。
●ラグランジアン形式
複素スカラー場のラグランジアンは次のようになる。
\[\mathcal{L}(\phi,\ \partial_\mu\phi) = \partial_\mu\phi^\dagger\partial^\mu\phi - m^2\phi^\dagger\phi\]
4章の余談で話したように、なぜこうなのかは問わないルールである。『ラグランジアンをこうしておけば、オイラーラグランジュ方程式によってスカラー場の運動方程式(クラインゴルドン方程式)が出てくるから』以上の意味はない。
場$\phi,\ \phi^\dagger$の共役運動量$\pi,\ \pi^\dagger$は
\[\begin{eqnarray*}\left\{ \begin{array}{l} \pi &=& \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\partial_0\phi} &=& \partial^0\phi^\dagger \\ \pi^\dagger &=& \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\partial_0\phi^\dagger} &=& \partial^0\phi \end{array}\right.\end{eqnarray*}\]
となる。また、4章でみたように、スカラー場のエネルギーと運動量は以下で与えられる。
\[\begin{eqnarray*} H = \displaystyle \int d^3\boldsymbol{x}\left\{ \pi^\dagger\pi + \boldsymbol{\nabla}\phi^\dagger \cdot\boldsymbol{\nabla}\phi + m^2\phi^\dagger\phi \right\}\\ \boldsymbol{P} = -\int d^3\boldsymbol{x}\ \frac{1}{2}\left\{\pi\boldsymbol{\nabla}\phi + (\boldsymbol{\nabla}\phi)\pi + \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad (\boldsymbol{\nabla}\phi)^\dagger\pi^\dagger + \pi^\dagger\boldsymbol{\nabla}\phi^\dagger \right\} \end{eqnarray*}\]
また、これに$\phi$と$\pi$に対する上のフーリエ変換の表式を代入することで、エネルギーと運動量の運動量空間表示を得る。地道に計算すれば出てくるので結果だけ示す。
\[\begin{eqnarray*} H &=& \int d^3\boldsymbol{k}\ E_\boldsymbol{k}\left\{ a^\dagger(\boldsymbol{k})a(\boldsymbol{k}) + b^\dagger(\boldsymbol{k})b(\boldsymbol{k}) \right\} \\ \boldsymbol{P} &=& \int d^3\boldsymbol{k}\ \boldsymbol{k}\left\{a^\dagger(\boldsymbol{k})a(\boldsymbol{k}) + b^\dagger(\boldsymbol{k}) b(\boldsymbol{k}) \right\}\end{eqnarray*}\]
●場の量子化
ここまでは、アインシュタインの関係式に量子論の置き換えをしたクラインゴルドン方程式に基づいて話を進めてきた。ここからさらに、看板どおり場を量子化する。2回目の量子化を行うため、第二量子化といわれることもある。
第二量子化は、場を演算子とみなして同時刻正準交換関係を以下のように導入することで実現される。ここで同時刻というのは、同じ時刻$t$での2つの演算子の関係を考えているということである。それ以外は量子力学の $[q_j,\ p_k]=i\delta_{jk}$と同じ気持ちであり、ただラベル$j, k$が無限自由度$x, y$になっただけである。
\[[\phi(t,\boldsymbol{x}),\ \pi(t,\boldsymbol{y})] = i\delta^3(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) = [\phi^\dagger(t,\boldsymbol{x}),\ \pi^\dagger(t,\boldsymbol{y})]\]
同様に$\phi(x)$の運動量表示を使うと、フーリエ係数に関して以下の交換関係を得る。
\[[a(\boldsymbol{k}),\ a^\dagger(\boldsymbol{k}')] = \delta^3(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}') = [b(\boldsymbol{k}),\ b^\dagger(\boldsymbol{k}')]\]
この交換関係を使うと、次のようにフーリエ係数$a, b$がエネルギーや運動量の生成消滅演算子になっていることが分かる。
\[\begin{eqnarray*} [H, a^\dagger] &=& \int d^3\boldsymbol{k}' E_{\boldsymbol{k}'} [a^\dagger a + b^\dagger b,\ a^\dagger] \\ &=& \int d^3\boldsymbol{k}' E _{\boldsymbol{k}'} a^\dagger \delta^3(\boldsymbol{k}' - \boldsymbol{k}) \\ &=& E_\boldsymbol{k} a^\dagger \end{eqnarray*}\]
\[\text{同様に、}[H, a]=-E_\boldsymbol{k}a,\ [H, b^\dagger]=E_\boldsymbol{k}b^\dagger,\ [H, b]=-E_\boldsymbol{k}b\]
実際、例えば、あるエネルギー$nE_\boldsymbol{k}$をもつ状態$\left\lvert n \right\rangle$を考えて、これに$a^\dagger$や$a$を作用させると、
\[Ha^\dagger \left\lvert n \right\rangle = (a^\dagger H + E_\boldsymbol{k}a^\dagger)\left\lvert n \right\rangle = (nE_\boldsymbol{k} + E_\boldsymbol{k})a^\dagger\left\lvert n \right\rangle = (n+1)E_\boldsymbol{k}a^\dagger \left\lvert n \right\rangle \]
\[Ha \left\lvert n \right\rangle = (aH - E_\boldsymbol{k}a)\left\lvert n \right\rangle = (nE_\boldsymbol{k} - E_\boldsymbol{k})a\left\lvert n \right\rangle = (n-1)E_\boldsymbol{k}a \left\lvert n \right\rangle \]
とエネルギーが一つ増減した状態を作ることができる。
そこで、真空状態$\left\lvert 0\right\rangle$をこれ以上固有値を下げられない状態として定義する。
\[a\left\lvert 0 \right\rangle = 0 = b\left\lvert 0 \right\rangle\]
真空状態に$a^\dagger(\boldsymbol{k})$を一つ作用させてみる。
\[\left\lvert k \right\rangle \equiv a^\dagger(\boldsymbol{k})\left\lvert 0 \right\rangle \]
これのエネルギーおよび運動量の固有値は、
\[\begin{eqnarray*} H\left\lvert k \right\rangle &=& \int d^3\boldsymbol{k}'\ E_{\boldsymbol{k}'}(a^\dagger a+b^\dagger b)a^\dagger(\boldsymbol{k})\left\lvert 0 \right\rangle \\ &=& \int d^3\boldsymbol{k}'\ E_{\boldsymbol{k}'}a^\dagger(\boldsymbol{k}') a(\boldsymbol{k}')a^\dagger(\boldsymbol{k})\left\lvert 0 \right\rangle \\ &=& \int d^3\boldsymbol{k}'\ E_{\boldsymbol{k}'}a^\dagger(\boldsymbol{k}')\delta^3(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k})\left\lvert 0 \right\rangle \\ &=& E_{\boldsymbol{k}}\left\lvert k \right\rangle \\ \text{同様に、}\boldsymbol{P} &=& \boldsymbol{k}\left\lvert k \right\rangle \end{eqnarray*}\]
となる。つまり、この状態はエネルギー$E_\boldsymbol{k}$、運動量$\boldsymbol{k}$をもつ質量$m=\sqrt{E_\boldsymbol{k}^2-\boldsymbol{k}^2}$の粒子が宇宙のどこかに一つ生成された状態とみることができる。ここでは、運動量表示の演算子$a^\dagger(\boldsymbol{k})$を作用させた。では、今度は座標空間の演算子$\phi^\dagger(x)$を真空に作用させるとどうなるか見てみる。
\[\begin{eqnarray*}\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle &=& \int\frac{d^3\boldsymbol{k}}{\sqrt{(2\pi)^3 2E_\boldsymbol{k}}} \left(a^\dagger(\boldsymbol{k})e^{ik\cdot x} + b(\boldsymbol{k})e^{-ik\cdot x} \right)\left\lvert 0 \right\rangle \\ &=& \int\frac{d^3\boldsymbol{k}}{\sqrt{(2\pi)^3 2E_\boldsymbol{k}}}\left\lvert k \right\rangle e^{ik\cdot x} \end{eqnarray*}\]
どう見てもこれは、運動量空間の1粒子状態から座標空間の1粒子状態へのフーリエ変換にほかならない。つまり、場の演算子$\phi^\dagger(x)$はいろいろな運動量成分の重ね合わせとして時空座標 $x=(t, \boldsymbol{x})$に粒子を一つ生成させる演算子であることが分かった。後の章で説明するが、実はフーリエ係数$a$と$b$はそれぞれ粒子と反粒子に対応している。つまり正確に言うと、場の演算子$\phi^\dagger(x)$はその表式から、粒子を一つ生成し、反粒子を一つ消滅させる演算子なのである。$\phi$はその逆である。そして、同様にすることで、$n$個の粒子状態は$n$個の演算子を作用させることで作り出すことができる。
これで、相対論の章で強調した場の量子論を導入する目的が達成された。すなわち、場の演算子によって、粒子の生成消滅を真空の励起状態として自然に記述できるようになったのである。
(余談)粒子とは真空の局所的な励起状態であるとか、エネルギーの塊であるなどとよく聞くが、これはエネルギーや運動量のスペクトルを行き来する生成消滅演算子を用いて表現できるという事実を指しているのだと思う。
●粒子の伝播
$\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle$は時空座標$x$に粒子が1つ生成された状態であった。ならば、これと$\phi^\dagger(y)\left\lvert 0 \right\rangle$との内積
\[\left\langle 0 \right\rvert \phi(y)\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle\]
は、粒子が$x$にいる始状態から$y$にいる終状態へ遷移する確率振幅を意味しているといえる。つまり、粒子が時空上の点$x$から$y$へ伝播する様子を表している。
ここで、伝播関数を以下のように定義する。
\[\left\langle 0 \right\rvert T\phi(y)\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle\]
$T$は時間順序積といわれ、時間的に過去から未来に向かって演算子を右から左へ並べる操作を行う演算子である。具体的には、階段関数$\theta(x)$を使って、
\[T\phi(y)\phi^\dagger(x) \equiv \theta(t_y-t_x)\phi(y)\phi^\dagger(x)+\theta(t_x-t_y)\phi^\dagger(x)\phi(y)\]
と表される。粒子の伝播は過去から未来へ起こることを保証するために、時間順序積が入っている。計算は大変なので補足に回すが、実際に伝播関数を計算すると以下を得る。
\[\left\langle 0 \right\rvert T\phi(y)\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle = \int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{ie^{-ik\cdot(x-y)}}{k^2-m^2+i\varepsilon}\]
分母の$k^2$は4元ベクトルのノルム $k^2\equiv k\cdot k=k_\mu k^\mu$である。また、$i\varepsilon$は階段関数$\theta$のフーリエ積分表示から来ており、積分変数として運動量$k$がいろいろな値をとるときに分母がゼロになってしまうことを防いでいる(極を実軸上からずらしている)。
伝播関数は、場の量子論を使って具体的な物理量を導く上で非常に重要な役割を演じる。なぜなら、粒子が何か場と相互作用しながら飛行するとき途中でどんなことが起こるのかは、中間状態(ファインマンダイアグラムの内線)で飛び交う粒子たちの伝播関数を使って求められるからである。
なお、ここで計算した伝播関数は、2つの時空点で定義された2点関数$\phi(y)\phi^\dagger(x)$を真空状態$\left\lvert 0 \right\rangle$で挟んだものとみることもできる。このように、なにか演算子を真空状態で挟んだ量を真空期待値と呼ぶ。
以上、自由複素スカラー粒子の理論を概観した。現実には、ヒッグス粒子が複素スカラー粒子として存在する。そのため、標準理論は複素スカラー場のラグランジアンを含んでいなければならない。また、素粒子実験の重要な物理量は、様々な演算子の真空期待値から計算され、ここで紹介した量が基礎となる。
(補足)伝播関数の導出
この計算をきちんと実行できないようであれば、場の理論をやっているとは言えない。計算力が乏しい私には、この程度の計算にもそれくらいの気概が必要である。
まず、$y^0 > x^0$のとき、$T\phi(y)\phi^\dagger(x)=\phi(y)\phi^\dagger (x)$なので、
\[\begin{eqnarray*}\left\langle 0 \right\rvert\phi(y)\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle &=& \left\langle 0 \right\rvert \int\frac{d^3\boldsymbol{k}d^3\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3\sqrt{2E_\boldsymbol{k}E_{\boldsymbol{k}'}}}\left(a(\boldsymbol{k})e^{-ik\cdot y}+b^\dagger(\boldsymbol{k})e^{ik\cdot y}\right) \\ &\quad &\quad\quad\quad\quad\quad\times\left(a^\dagger(\boldsymbol{k}')e^{ik'\cdot x}+b(\boldsymbol{k}')e^{-ik'\cdot x}\right) \left\lvert 0 \right\rangle \\ &=& \int\frac{d^3\boldsymbol{k}d^3\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3\sqrt{2E_\boldsymbol{k}2E_{\boldsymbol{k}'}}}\left\langle 0 \right\rvert a(\boldsymbol{k})a^\dagger(\boldsymbol{k}')e^{-ik\cdot y+ik'\cdot x}\left\lvert 0 \right\rangle \\ &=& \int\frac{d^3\boldsymbol{k}d^3\boldsymbol{k}'}{(2\pi)^3\sqrt{2E_\boldsymbol{k}2E_{\boldsymbol{k}'}}}\left\langle 0 \right\rvert\delta^3(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')e^{-ik\cdot y+ik'\cdot x}\left\lvert 0 \right\rangle \\ &=& \int\frac{d^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^32E_\boldsymbol{k}}e^{-ik\cdot(y-x)} \end{eqnarray*}\]
これの前には階段関数$\theta(y^0- x^0)$がかかる。これのフーリエ積分表示は
\[\theta(y^0-x^0)=-\frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^\infty dz\frac{e^{-iz(x^0-y^0)}}{z-i\varepsilon}\]
と表される。$\varepsilon$は任意の微小量である。これは右辺の複素積分を実行することで確かめられる。積分路を次のようにとって、コーシーの積分定理を用いればよい。
よって、$\theta(y^0- x^0)\left\langle 0 \right\rvert\phi(y)\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle$は
\[\begin{eqnarray*} \theta(y^0- x^0)\left\langle 0 \right\rvert\phi(y)\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle &=& -\frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^\infty dz\frac{e^{-iz(x^0-y^0)}}{z-i\varepsilon}\int\frac{d^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^32E_\boldsymbol{k}}e^{-ik\cdot(y-x)} \\ &=& -\int\frac{dzd^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^42E_\boldsymbol{k}}\frac{ie^{-iz(x^0-y^0)-ik\cdot(y-x)}}{z-i\varepsilon} \\ &=& -\int\frac{dzd^3\boldsymbol{k}}{(2\pi)^42E_\boldsymbol{k}}\frac{ie^{i(z-E_\boldsymbol{k})(y^0-x^0)+i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})}}{z-i\varepsilon} \\ &=& -\int\frac{d^4k}{(2\pi)^42E_\boldsymbol{k}}\frac{ie^{-ik\cdot(x-y)}}{k^0+E_\boldsymbol{k}-i\varepsilon} \end{eqnarray*}\]
最後の等号で、$k^0\equiv z-E_\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{k}\rightarrow -\boldsymbol{k}$の置き換えを行い、$dk^0d^3\boldsymbol{k}\rightarrow d^4k$と書いた。当然、$k^0\neq E_\boldsymbol{k}=\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}$ではなくなっていることに注意。これを$k$はオフシェルにあるという。
$x^0 > y^0$のときも同じようにやることで、求めたいものは最終的に、
\[\begin{eqnarray*} \left\langle 0 \right\rvert T\phi(y)\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle &=& \theta(y^0- x^0)\left\langle 0 \right\rvert\phi(y)\phi^\dagger(x)\left\lvert 0 \right\rangle + \theta(x^0- y^0)\left\langle 0 \right\rvert\phi^\dagger(x)\phi(y)\left\lvert 0 \right\rangle \\ &=& \int\frac{d^4k}{(2\pi)^42E_\boldsymbol{k}}\left(-\frac{ie^{-ik\cdot(x-y)}}{k^0+E_\boldsymbol{k}-i\varepsilon}+\frac{ie^{-ik\cdot(x-y)}}{k^0-E_\boldsymbol{k}+i\varepsilon}\right) \\ &=& \int\frac{d^4k}{(2\pi)^42E_\boldsymbol{k}}\frac{2E_\boldsymbol{k}ie^{-ik\cdot(x-y)}}{\left(k^0\right)^2-{E_\boldsymbol{k}}^2+i\varepsilon} \\ &=& \int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{ie^{-ik\cdot(x-y)}}{k^2-m^2+i\varepsilon} \end{eqnarray*}\]
となる。3つめの等号の$\varepsilon$は適当な微小量として新たに置きなおされたものである。最後に$E_\boldsymbol{k}^2=\boldsymbol{k}^2+m^2$を用いて4元ベクトルのノルムの表式に書き換えた。このように、この計算は独特なテクニックをいくつも要する。




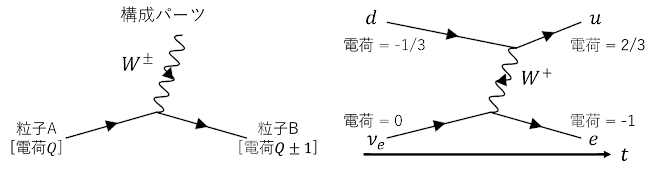

コメント
コメントを投稿